2025年8月、豊橋市で開催した「校区サポーター養成講座(全3回)」が無事終了しました。
テーマは「SNSがもっと楽しくなる!市民向け発信力アップ講座」。
「せっかく投稿しても誰にも届かない気がする」
「コメント対応ってどうすればいいの?」
そんな悩みを抱える市民の方々に向けて、SNSの発信力を高め、地域の魅力をより多くの人に届けられるようになるための学びの場でした。
この講座を通じて私たちが感じたのは、発信は「技術」だけではなく「意義」と「責任」に裏打ちされてこそ力を持つ、ということです。以下では、3回の講座を振り返りながら、その手ごたえを共有したいと思います。
第1回|SNSマーケティング入門 —— 発信に軸を持つ
最初のテーマは「フォロワーがみるみる増える、SNSマーケティングのコツと実践」。
講師はWonder Design CEOの早瀬由芙さん。デザイン思考を用いた新事業開発の他、グラフィック&プロダクトデザイン、ウェブサイト制作などスタートアップや新事業開発に関わる幅広い業務支援を行っている実務家であり、企業向けにお話される機会が多い早瀬さんが一般向けに講演される貴重な機会となりました。
この講座では「SNSフォロワー数=希少性×需要」というシンプルな公式をもとに、自分の強みと地域のニーズを掛け合わせる大切さを学びました。受講者同士のワークでは「私だから伝えられることは何か?」を語り合い、笑顔やうなずきが自然と生まれていたのが印象的でした。
“豊橋の暮らしやすさを一番知っているのは、住んでいる私たち自身”
そんな原点に立ち返る時間でもあり、参加者の方は初対面ながらそれぞれの知る「まちの良さ」を互いにシェアされながら親交を深めていました。
第2回|Instagram投稿実務講座 —— 「魅せる」から「共感される」発信へ
2回目は、フォロワー4.9万人のInstagramアカウント「いいじゃん三河」を運営するジャンミカさんによる講座。ジャンミカさんは豊橋を中心に三河エリアのリアルな生活情報・お得情報を発信し続け、主婦層を中心に絶大な信頼と人気を誇るインスタグラマーです。
講座では「校区名を入れると地域に信頼されやすくなる」「発信は“魅せる”から“共感される”へ」というメッセージも。参加者は地元のお店や季節の風景を題材に投稿文を作成したり、発信する際のヒントやアイディアを実践的に学びました。
地域情報を「自分の言葉」で伝えることの価値に気づいた方が多く、「ただ写真を載せるのではなく、背景のストーリーを添えたら反応が違った」という声が寄せられました。
第3回|メディアリテラシー講座 —— 情報とどう向き合うか
最終回は、元Wikipedia日本語版管理者の海獺(らっこ)さんによる「情報時代のSNSとの付き合い方」。情報時代の受発信のプロとして、「ねほりんぱほりん」「アシタノカレッジ」「宮藤さんに言ってもしょうがないんだけど」などに多く出演されています。
「情報は食べ物のようなもの。何を取り入れるかで、考え方は形づくられる」。
その言葉に、会場の空気が一瞬静まり返ったのを覚えています。
海獺さんの講座はフェイクニュースや炎上の事例を通して「シェアする前に立ち止まる」「事実・意見・感情を区別する」ことの重要性が語られました。発信の楽しさと同時に、責任とリスク管理の必要性を学ぶ濃密な2時間でした。
受講者の声
- 「SNSを“日記”ではなく“役立つメディア”として考えられるようになった」
- 「校区名を入れるだけで投稿の信頼度が高まることを体感した」
- 「炎上リスクや個人情報の扱いを知り、安心して発信できそう」
単なるスキル習得にとどまらず、“自分が地域でどう発信していくか”を考えるきっかけになったようです。
▼校区サポーター farmers2021 さんの投稿
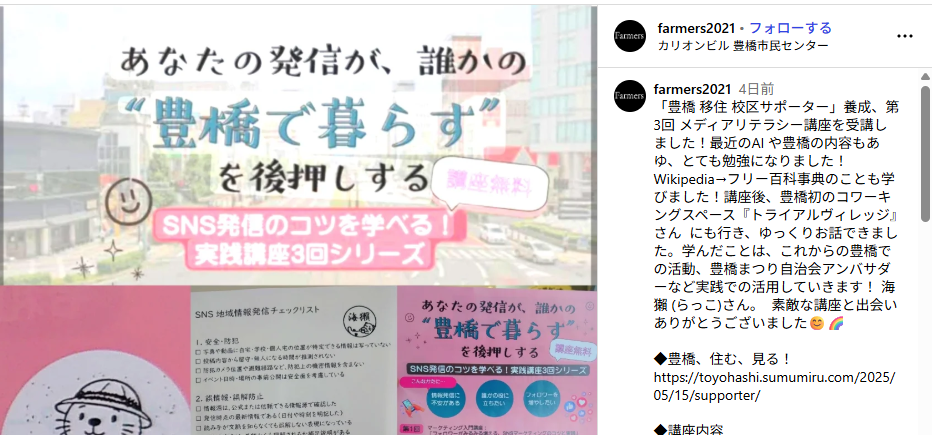
これからの校区サポーターへ
今回の講座で芽生えた学びは、地域メディア「sumumiru.(スムミル)」にもつながっていきます。
受講者の投稿がsumumiru.で紹介されることで、豊橋の校区ごとの暮らしの魅力が、さらに広く・深く伝わっていくでしょう。
校区サポーターの役割は「地域の小さな魅力をすくいあげ、それを言葉と写真で伝えること」。
その一歩を踏み出した皆さんとともに、これからも豊橋の魅力を発信し続けていきます!

コメント